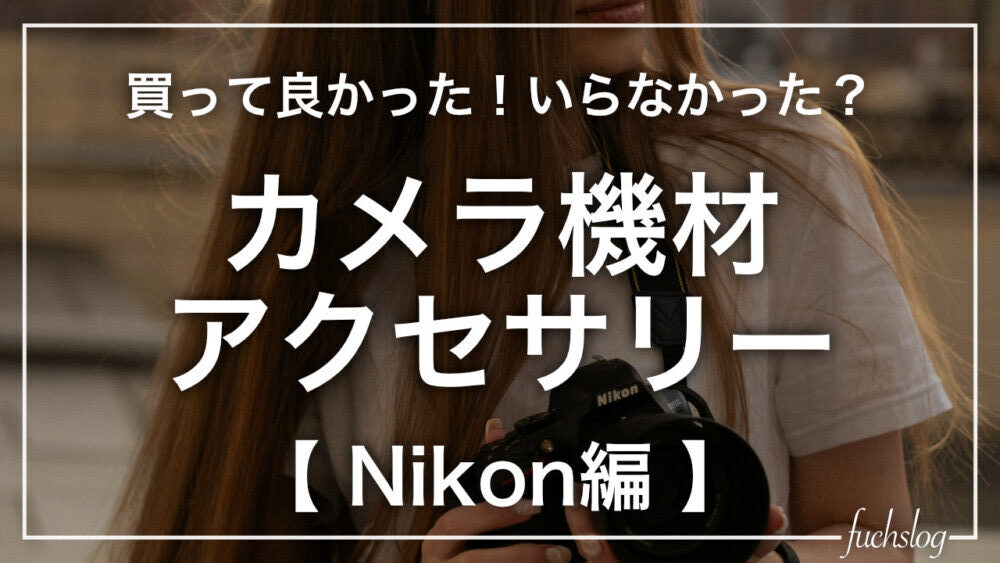はじめに
「カメラを始めたけど、どんな機材を揃えればいいか分からない…」
そんな悩みを持つ初心者の方に向けて、Nikon Z6IIでカメラライフを楽しんでいる筆者が、実際に買ってよかったもの、正直いらなかったものを忖度なしでご紹介します。
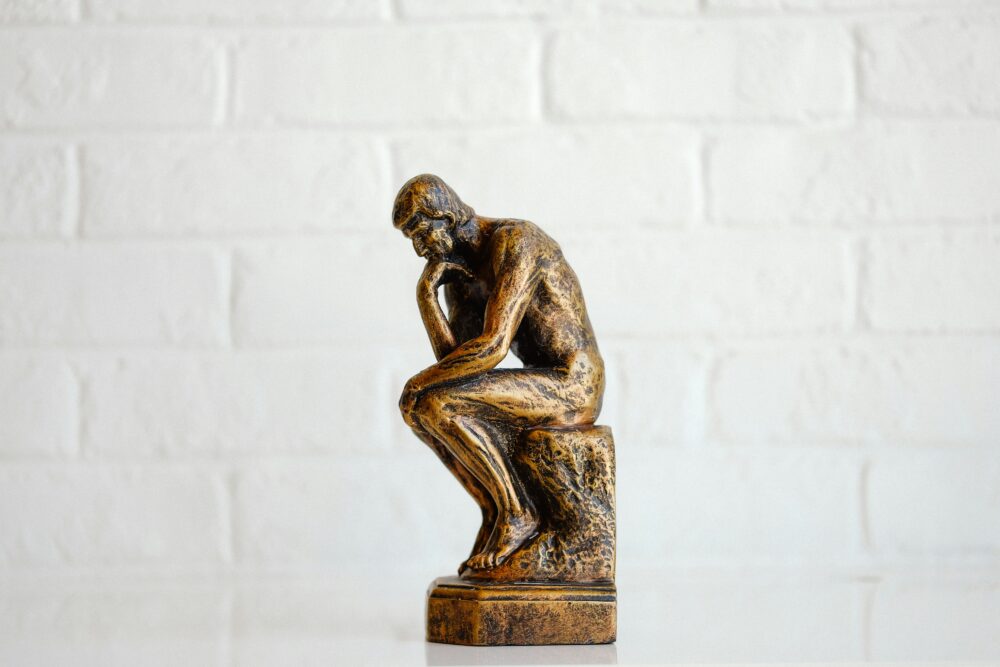
私自身も初めてのカメラ選びやアクセサリー購入で失敗した経験があります。この記事が、皆さんの無駄な出費を減らし、より快適な撮影ライフを送るための手助けになれば嬉しいです。
撮影の要となる「カメラ本体とレンズ」
まずは、撮影に欠かせないカメラ本体とレンズについてです。
ミラーレスカメラ「Nikon Z6II」

| 手頃な価格で、フルサイズセンサーの写真が撮れる。 (最近ならZ5IIがオススメ) |
| チルト式のため横画面では、ハイアングル・ローアングルが非常に撮りやすい。 |
| 風景写真やポートレートには丁度いいサイズ (趣味・業務の中間といったイメージ) |
| チルト式のため縦画面では、ハイアングル・ローアングルが撮りにくい。 |
| 最新機種と比べるとAF弱いため、動きが素早い被写体には向かない。 |
キヤノンとニコンで迷った末、筆者が選んだのは、ニコンのミラーレスカメラ「Z6II」です。当時、24-120mm f4/S のレンズと同梱された限定キットが非常にお得だったので、飛びつきました。
Z6IIIも出ていましたが高価ですし、何より風景やポートレートなど、動きの少ない被写体を撮ることがほとんどだと思っていたので、このカメラで十分でした。正直、中古のZ6でも良かったかもしれません。
動く被写体(鉄道、飛行機、スポーツなど)をメインに撮影される方は、Z8やZ9、最新のZ6IIIといった上位モデルを検討すべきでしょう。一方で、動く被写体はあまり撮らず、高画素で細部までこだわりたい方には、Z7系がおすすめです。
補足ですが、NikonはFマウント(一眼レフ用)レンズが中古市場で安く手に入るため、Dシリーズ(一眼レフ)を選ぶのも良い選択肢だと思いました。ただし、ミラーレスカメラに比べてボディが重く、AF性能も最新モデルには劣るので悩みどころでもあります。
非常に便利だった標準ズームレンズ「NIKKOR Z 24-120mm f/4 S」

| 一本で何でも撮れるような汎用性の高さ。 (広角〜中望遠) |
| シャープネスで解像度が高い。 |
| 単焦点レンズに比べてF値が大きく、暗い場所では不利。 |
このレンズは「何でも撮りたい」という初心者にとっては非常に便利でした。Z6IIIのレンズキットにもなっており頷けます。(当時は限定でZ6IIのレンズキットになっていました)
24mmの広角で風景、50mmや85mmでポートレート、120mmで動物や花(ハーフマクロ)など、一本で約9割のシーンをカバーできる体感があります!
ただ、24mmから120mmという幅広い焦点距離の中から、どの場面でどの画角を選べば良いのか、初心者の方には迷ってしまうかもしれません(筆者はそうでした)。
「何でもできる は 何も出来ない」と言ったように、特定の状況下で大活躍するレンズではありません。いつでも、平均点を出せるようなレンズと言ったら分かりやすいかもしれません。
また、ボケ味を追求する単焦点レンズとは異なり、f4通しのためボケは弱めです。ただ、120mmといった中望遠域であれば、それなりに背景をぼかすことは可能です。
買ってよかった単焦点レンズ「NIKKOR Z 50mm f/1.8 S」

| 手頃な価格で、Sラインの高品質な単焦点レンズが楽しめる。 |
| 背景が綺麗にボケる。 |
| 非常にシャープネスで解像度が高い。 |
| パンケーキレンズやコンデジと比べると、サイズが大きい。 |
標準ズームレンズではF値が大きいため、徐々に背景をぼかした単焦点レンズが欲しくなってきます。
(F値の数字が小さいほど、明るく、背景をぼかした写真が撮れます)
そこで、標準域の単焦点で一番、手が出しやすく評判の高いレンズの50mm f1.8を購入しました。f1.4とも迷いましたが、当時は柔らかい雰囲気よりも現代的なシャープな写真が撮りたかったのでSラインのf1.8に選択しました。
結論から言うと、買って大正解でした。
F値が1.8と明るいため、背景をきれいにぼかすことができます。(今まではF値4が開放)
何より、焦点距離が50mmだけなので、構図を考えることに集中しやすく、撮影そのものが楽しくなりました。このレンズで撮った写真は、スマホとは比べ物にならないくらい別格の写りです。
正直いらなかった…望遠レンズ「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S」

| 焦点距離が最短で70mmのため、ポートレートや動物、風景撮影など意外と活用シーンが多い。 |
| 単焦点レンズが要らなくなるほど、別格の写り。 |
| 三脚を利用することで、本体が回転し縦画面でも撮影しやすくなる。 |
| 今までご紹介したレンズの中で、一番高価。 |
| 大きくて重く、取り回しにくい。 |
標準ズームレンズも明るい単焦点レンズもあると、今度は望遠レンズが欲しくなります。
そして、今までの経験から、ズームも出来て明るいレンズの代名詞である、「大三元レンズ」が欲しくなりました。
結論から言うと、筆者の趣味レベルでは必要ありませんでした。実際に使ってみると丁度いい焦点距離ですし、風景やポートレート撮影などでも活躍するレンズです。写りも抜群で、単焦点レンズが不要に思えるほどの別格の性能でしたが、とにかく大きくて重く、取り回しが非常に大変でした。
このクラスのレンズは、プロやハイアマチュア向けだと実感しています。初心者には少しハードルが高かったのかもしれません。
撮影を支える「必須」のアクセサリー
次に、カメラを守り、撮影をより快適にするために、絶対に持っておくべきアクセサリーをご紹介します。
レンズフィルター
| お手軽にレンズを保護。 |
| 描写力の低下は全く気にならない。 |
これは絶対に買うべきです。特にレンズフードをつけずに撮影する方には必須。私自身、動物園の手すりにぶつかった際にレンズフィルターにあたり、レンズ本体が守られた経験があります。
何より、チリや埃なども保護にもなるので、安心を買うと思えば安いものです。
高価なものでなくても、通常の保護フィルターで十分です。こだわりのある方は、高級レンズフィルターを検討してみて下さい。
筆者には、高級フィルターと通常のフィルターとの違いが目に見えるほど分かりませんでした。
記録用メモリー(SDカード)
| 写真や動画を保存するために必須。 |
| 最近では金額もかなりお手頃。 |
写真や動画を保存するためには不可欠なアイテムです。個人的には、撮影後にすぐにクラウドサービス(Amazon Photoなど)に保存しているので、128GBもあれば十分だと感じています。
長期間、パソコンやクラウドに保管出来ない方は、大容量の方が沢山保存できるので安心です。
ただ、少ない容量のSDカードを複数持っていても、破損リスクの分散になるので決して悪い選択ではないと考えています。
保護ガラスフィルム
| ディスプレイを簡単に保護。 |
| 商品によっては指紋が目立つ。 |
最近のカメラはタッチパネル式で、画面を触る機会が多いため、傷がつく恐れがあります。
チルト式だと画面が剥き出しになっているので、安心して使うためにも貼っておいた方が良いでしょう。
クリーニング用品セット(本体・レンズ用)
| カメラやレンズを清潔に保てる。 |
| 価格もお手頃。 |
撮影中にゴミやホコリがレンズにつくと、写真に影響が出てしまいます。
自分で手入れできる簡単なセットを一つ持っておくことをおすすめします。
防湿庫「オートクリーンドライ」
| 手間要らずで除湿できる。 |
| 光触媒のクリーン機能があり、菌の分解除去や脱臭が出来る製品もある。 |
| ランニングコストも1日1円程度と安い。 |
| 初期費用は高い。 |
カメラやレンズはカビに弱く、湿気の多い日本では必須のアイテムです。簡易的な防湿ボックスだと、吸湿剤の交換が面倒になりますが、防湿庫なら手間がかかりません。大切な機材を長く使うためにも、ぜひ購入をおすすめします。
ランニングコストも1日1円程度なのですが、初期費用としてレンズ代程の金額がかかってしまうので、どうしても節約したい方は、防湿ボックスと除湿剤を使って、運用することをオススメします。
防湿庫にはペルチェ方式と乾燥剤方式の2種類がありますが、長年愛用するなら耐久性能の高い乾燥剤方式の方が安心です。
東洋リビングの製品は、光触媒でカビ菌などの分解・除去や脱臭効果も期待できるので、おすすめです。
あると便利な「あると便利」なアクセサリー
絶対に必要ではないけれど、あると撮影が格段に楽しくなるアイテムです。
カメラストラップ(首掛けタイプ)
カメラストラップ「ニンジャストラップ」
| バッグの出し入れが要らないため、速写性が高い。 |
| 簡単に伸縮できるため、歩きながらの撮影に適している。 |
| 余ったストラップがだらんと垂れてしまい、見栄えは悪い。 (折りたたんで引っ掛ける事が出来るが、速写性が落ちる) |
首掛けタイプと手首タイプの2種類を使い分けています。どちらも瞬時にカメラを構えることができるため、シャッターチャンスを逃しにくいです。
伸縮するタイプは体にフィットして歩きやすく、移動時も安定させられます。
ニンジャストラップを購入しましたが、大正解です。余ったストラップがだらんと垂れてしまうので、見た目は少々イマイチですが、伸縮のしやすさという点の機能性は抜群です。
クイックリリースシステム「PGYTECH」
| 簡単にカメラ本体とクランプを取り外しできる。 |
| クランプがあることで、ストラップをカメラの真下に取り付けられる。 (望遠レンズなど、長いレンズに最適。) |
| クランプ自体の取り外しは少し、手間がかかる。 |
| 平面な場所にカメラを置いたときに安定しにくくなる。 |

| カメラストラップとカメラを簡単に取り外しできるようになる。 |
| ストラップが捩れても、360度回転するので絡まない。 |
| 標準セットでオレンジとブラックが2つずつ同梱されているので嬉しい。 |
| 見た目は少し安っぽい。 |
クイックリリースを併用すれば、ストラップとカメラ本体の付け外しを瞬時にできて非常に便利です。

PBYTECHのクイックコネクター(ビーズ状のもの)は通常のストラップを、着脱できるようにすることができます。
なぜ、既にクイックリリースがあるのにさらに、コネクターを装着しているかと言いますと、逆の肩に切り替えられるようになるからです。
※これは、ニンジャストラップのように肩にかける向きが決まっているストラップに対して有効です。
左右対称で、どちらにかけても伸縮できるようなストラップには必ずしも必要ではありません。
また、コネクター部分が360度回転するので、ストラップが絡まないのが非常に楽です。引っ張れば簡単にねじれが無くなります。
カメラストラップ(手首タイプ)

| いざという時に、落とす危険性が少なくなり、安心して使える。 |
| ハイアングルやローアングルなど、取り回しの良さが一番良い。 |
| 常に右手に付けているので、首掛けのストラップより疲れがち。 |
手首タイプは、特に使いやすく、自由度が高いのが魅力です。低いアングルからの撮影など、様々なシーンに対応できます。何より、短いのでバッグにもスッと入ります。
カメラバッグ(ショルダー)
| リュックタイプより簡単にカメラを取り出せる。 |
| 片方の肩に負担がかかる。 (適度に逆にしたい) |
ショルダータイプのカメラバッグは、瞬時にカメラを取り出せるのが最大の魅力です。街歩きや気軽に撮影に出かける際に非常に便利だと感じました。ただし、片方の肩に負担がかかりやすいので、重い機材を長時間持ち運ぶ際には注意が必要です。適度に逆の肩に負担を分散させましょう。
筆者の場合、手首用のストラップを使う時は、大体カメラバッグ(ショルダー)を使います。
吸湿ラッピングクロス
| 簡単にカメラの保護・調湿ができて安心。 |
| 天日干しで調湿機能が復活する。 |
| 消臭機能も有り、清潔に保てる。 |
| 目印がないので、調湿機能が作用しているか分かりにくい。 |
防湿庫を導入する前は、このクロスが大活躍してくれました。レンズやカメラを包んでおくだけで湿気を吸収してくれるので、手軽に機材を守ることができます。
クリーニング用品(センサー用)
| 専用のものを使わずに、センサークリーニングできる。 |
| いざという時、ドラッグストアでも購入できる。 |
| 初心者には難しい場合がある。危険。 |
センサークリーニング用のスワブで上手くいなかった時に、とある記事を参考に購入した無水エタノール。こちらと綿棒(なるべく毛が抜けないもの)を利用したところ、簡単に綺麗になりました。
ただ、センサー部分の扱いは危険なので、お店でクリーニングしてもらう方が無難かと思います。
私が「いらなかった」と感じたもの
最後に、個人的にはあまり活躍しなかったアイテムをご紹介します。
三脚「VANGUARD」
| 星空・風景・動物など特定の被写体で大活躍。 |
| 長時間露光撮影ができる。 |
| 取り回しは基本的に悪い。 |
三脚は撮影目的によって大きく必要性が変わるアイテムです。また、昨今のカメラは手ぶれ補正が非常に強力になっており、筆者のようにスナップ写真を主に撮影する程度の人には不要かもしれません。
しかし、夜景や星空、野鳥などをじっくり構えて撮影したい方には、必須のアイテムになります。
記録用メモリー(CF Expressカード)
| 非常に早いデータ移動ができる。 |
| 専用のリーダーが必要。 |
| 金額も高価。 |
趣味レベルだと正直、不要で高価な買い物でした。使い勝手自体は最高で、データ処理の速さには驚かされます。筆者の場合は最終的に、Amazon Photoにアップロードするのに時間がかかるのでそこまでの時短にはなりませんでした。
専用のカードリーダーも必要になるため、予算に余裕があり、とにかく高速なデータ転送を体験したい方にはおすすめです。
予備バッテリー
私は頻繁に電源のオンオフを行うため、バッテリーの消費が少なく、正直必要ありませんでした。数日の旅行程度であれば、1つで足ります。
電源をつけっぱなしにしたり、動画を長時間撮影する方にとっては、あると安心なアイテムでしょう。
USB給電もできるので、モバイルバッテリーでも有りかと思います。
カメラバッグ(リュック)&カメラホルスター
| カメラに加えて、多様なレンズや備品を運ぶことができる。 |
| ショルダータイプのバッグと比べて、取り出しがしにくい。 |
カメラバッグ(リュック)は、たくさんのレンズを持ち運ぶ方には良いかもしれませんが、私はあまり多くのレンズを持って出かけないので、必要ありませんでした。横から取り出せるタイプでも、やはり取り出しやすさはショルダータイプには劣ると感じました。
望遠レンズを使用する方や、複数のレンズを使用する方にとっては必須アイテムとなるでしょう。
| 瞬時にカメラの取り外しができる。 |
| 片方の肩に負担がかかる。 |
カメラホルスターは、リュックを使用している時に、簡単に一時的に装着出来るように購入しましたが、片方の肩にだけ負担がかかってしまうので、ほとんど使っていません。
クリーニング用品スワブ(センサー用)
| 専用のスワブでセンサーをクリーニングできる。 |
| 初心者には難しい場合がある。 |
センサーのゴミが気になって、自分でクリーニングキット(スワブ)を購入したことがありましたが、完全にゴミを取り切ることはできませんでした。
最終的には、前述で記載した、無水エタノールと綿棒の方で解決しました。
こちらも同様に、慣れない方はお店に依頼する方が安心かもしれません。
まとめ
カメラの機材選びは、どんな写真を撮りたいか、どんな撮影スタイルかによって大きく変わります。
まずは「必須アイテム」から揃えて、自分がどんな機材やアクセサリーを必要とするかを経験から見極めることが大切です。いきなり高価な機材を全て揃える必要はないです。
使いながら、不便に感じた事を解決できる物を買っていく事が一番大事かと思います。
この記事が、皆さんのカメラ選びの参考になれば幸いです。
カメラを購入して3ヶ月。当時のお気に入りのスナップ写真をご紹介。

カメラ:Z6II
レンズ:NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

最後までご覧いただきありがとうございました!